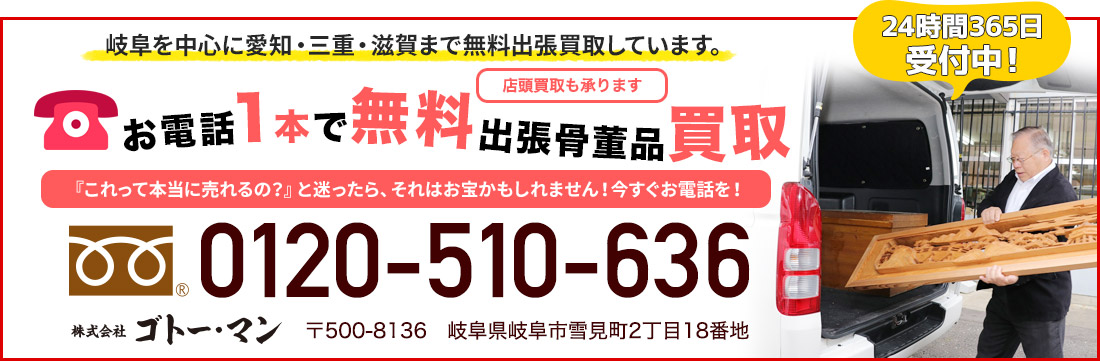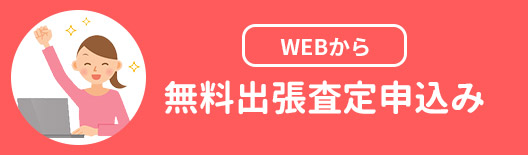Q&A一覧
Q&Aカテゴリー
お問合せ (6)お支払い方法 (1)来店持込 (1)査定依頼 (6)査定金額 (3)楽器 (5)無料出張買取 (2)買取依頼 (16)買取価格 (4)遺品整理 (16)骨董品について (680)
あなたの人形、買取りできる?買取り不可の基準とは?
人形は、多くの家庭で大切にされ、時には世代を超えて受け継がれる文化的なアイテムです。しかし、時と共に処分したいと考える方も多いのが現実です。そこで、人形の買取についてお話ししましょう。
お買取りできるお人形とは? 雛人形・五月人形の買取可能性 雛人形や五月人形は、日本の伝統的な祝い事に欠かせないアイテムです。しかし、これらの...続きを読む
肥後象嵌・透(ひごぞうがん・すかし)とは何?そしてその技を持つ人間国宝には誰がいるのか?
江戸時代から続く日本の伝統技術、肥後象嵌・透。この技法は、熊本県を中心に発展した独特の金工技術で、その技術保持者として人間国宝に認定されたのが米光光正です。
米光光正と肥後象嵌 米光光正は、1888年に熊本県坪井に生まれました。彼は幼いころに父を亡くし、15歳から祖父と叔父に金工の技術を学び始めました。 &nbs...続きを読む
不動の人気の北大路魯山人作品の魅力は何?
今回は、日本の伝統工芸と美食の世界に大きな影響を与えた一人、北大路魯山人の作品の魅力に迫ります。
北大路魯山人とは 北大路魯山人は、1883年京都に生まれた日本を代表する多才な芸術家です。彼は不遇の幼少期を経て、書、絵画、版画、篆刻など多岐にわたる分野で才...続きを読む
茶道具買取の歴史、いつからどのように始まったのか?
茶道具の歴史について深く掘り下げると、日本の文化や歴史と密接に関連していることがわかります。本記事では、茶道具の歴史と、その買取についての変遷を紐解いていきましょう。
茶道具の歴史の始まり 茶道具の歴史は、日本の茶道の歴史と密接に結びついています。その起源は平安時代末期にさかのぼります。 平安時代末期から室...続きを読む
終活のための生前整理、いつとどう始める?
今回は、生前整理の始め方や進め方、そのメリットや注意点について詳しく解説します。
生前整理とは? 生前整理は、自分の人生の終わりに備えて、物品や財産などを整理することです。この活動は終活の一部として行われ、自分のこれまでの人生を振り返り、自...続きを読む
三味線を売る前に知っておきたい!買取価格を左右するポイントは何ですか?
三味線は日本の伝統的な楽器で、骨董品としてもその価値が認められています。三味線を売る前に、三味線の買取価格に影響を与える主要なポイントを解説します。
三味線は日本の伝統的な楽器で、骨董品としてもその価値が認められています。三味線を売る前に、その価格を左右する要因を知ることは非常に重要です。以下に、三味線の買取...続きを読む
軍事切手を高く買い取ってもらうにはどうすればいい?
軍事切手のコレクションは、歴史愛好家や切手収集家にとって特別な魅力を持っています。これらの切手を高く買い取ってもらうためには、いくつかの重要なポイントがあります。
軍事切手は歴史的な価値と希少性から、切手収集家や歴史愛好家にとって非常に魅力的なアイテムです。これらを高く買い取ってもらうためには、いくつかの重要なポイントがあ...続きを読む
六古窯って何?常滑焼の魅力とは?
日本の陶磁器というと、多くの人が思い浮かべるのは「六古窯(ろっこよう)」かもしれません。この記事では、六古窯の一つである常滑焼を中心に、日本の古陶磁器の魅力について深堀りします。
日本における陶磁器の歴史は深く、その中心に位置するのが「日本六古窯」です。この記事では、六古窯のひとつである常滑焼を中心に、日本の古陶磁器の魅力を掘り下げてみま...続きを読む
アンティーク銀器の買取査定に挑む前に知っておくべきポイントは?
アンティーク銀器は、その歴史的価値と美しさで多くのコレクターや愛好家に愛されています。買取査定に出す前に知っておくべき重要なポイントを解説します。
アンティーク銀器は、その独特な魅力と歴史的価値で多くのコレクターや愛好家を魅了します。買取査定を考えている方へ、査定に臨む前に知っておくべき重要なポイントを詳し...続きを読む