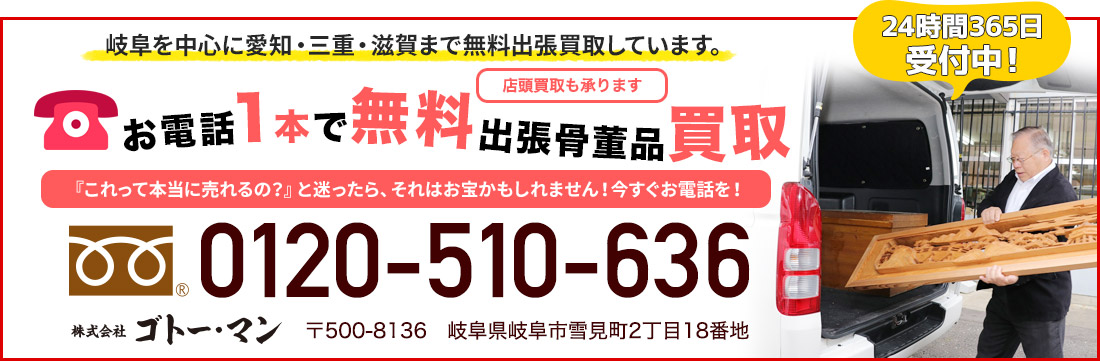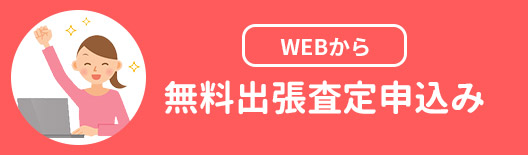人間国宝・松井康成の世界!練上手の美と買取相場を解説。
人間国宝・松井康成が極めた「練上手」の技法と、その作品の買取相場について解説します。
骨董品の世界には、時代を超えて評価される“技”があります。中でも、「練上手(ねりあげで)」という言葉にピンときた方は、相当な陶芸好きか、あるいは松井康成という名前をご存じの方かもしれません。
今回は、笠間焼の人間国宝・松井康成が極めた「練上手」という技法にスポットを当て、その芸術性や作品の魅力、そして現在の買取相場について、一般の骨董ファンの方にもわかりやすくお届けします。
松井康成とは ― 陶芸に人生を捧げた人間国宝
松井康成(まつい こうせい)は1927年、長野県に生まれました。戦時中に父の故郷である茨城県笠間町へ疎開したことをきっかけに、笠間焼と出会います。
10代の頃にはすでに、地元の奥田製陶所にアルバイトとして通い、実際に陶芸に触れながら腕を磨いていきました。大学在学中には日本画も学び、卒業後は僧侶としての道を歩みながら、境内にあった古い窯を自らの手で復元。以降、独自の美意識を貫きながら、陶芸家としての道を極めていきます。
1968年には陶芸家・田村耕一に師事し、以後は「練上手」の研究に没頭。1988年には紫綬褒章、1993年には重要無形文化財保持者、いわゆる“人間国宝”に認定されました。
練上手(ねりあげで)とは何か?
「練上手」とは、複数の色の異なる粘土を練り合わせ、切ったり伸ばしたり、時にはろくろで回しながら、陶器の中に模様を“織り込む”ように作り出す技法です。
簡単に言えば、粘土自体に模様を仕込んでいくのが特徴。しかし、粘土にはそれぞれ異なる収縮率があるため、焼成時にひび割れや破損が起きやすいという大きな難点がありました。
この難しさゆえ、長らく本格的に取り組む陶芸家は少なかったのですが、その限界に挑み、むしろ“ひび割れ”すらも模様として取り込むという独創的なスタイルでこの技法を進化させたのが、松井康成なのです。
松井康成が確立した新たな練上手の世界
松井康成が練上手を単なる模様作りの技法にとどめなかったことが、人間国宝に認定された大きな理由のひとつです。
1975年には、ろくろの回転運動を応用して模様を描く「嘯裂(しょうれつ)」という独自のスタイルを確立。この技法により、練上手の世界に立体的な動きや流れを持ち込むことに成功しました。
このように、手びねり中心だった練上手に動的な造形を取り入れたことで、練上手はより芸術性の高い技法へと進化を遂げます。以降、「破調練上」「晴白練上」「萃瓷練上」など、さらなる派生技法を生み出していきます。
松井康成の作品は、偶然性を大切にしていたとも言われています。練上手では焼成時にどんな模様が出るか予測できない部分も多く、まさに“土との対話”を重ねた作品群と言えるでしょう。
松井康成の代表作とその魅力
松井康成の作品には、どこか静謐で、宗教的な気配すら感じさせる美しさがあります。シンメトリーでありながら不均衡を内包し、偶然に生まれる模様を完璧にコントロールすることなく受け入れる――そこには日本人の“侘び寂び”の美意識が色濃く反映されています。
特に評価が高いのは、大型の壺作品。ろくろで仕上げたうねるようなフォルムに、複数色の粘土が織りなす縞模様、ひび割れ模様が混在し、唯一無二の存在感を放ちます。
また、白を基調とした「晴白練上」は、非常に清潔感があり、茶人の間でも高く評価されています。
松井康成作品の現在の買取相場
では、実際に松井康成の作品は、現在どのような価格で取引されているのでしょうか。
結論から言えば、その評価は作品の種類や状態によってかなり幅があります。市場価格はおおよそ以下のようなイメージです。
-
練上手の小品(ぐい呑み、皿など):3〜10万円前後
-
中サイズの作品(壺、花器):10〜30万円
-
大型の壺や一点ものの展覧会出品作:50〜100万円以上
-
晩年の大作・個展出展作品:100万円以上の査定がつくことも
特に人気が高いのは、上記でも触れた「破調練上」「晴白練上」「萃瓷練上」といった高度な技法を用いた作品です。これらは、制作に時間と手間がかかる上に、完成度も非常に高いため、高額査定につながりやすい傾向があります。
逆に、練上手以外の技法(堆瓷など)を用いた作品や、小型の花器、量産された作品などは、1万円前後で取引されることも珍しくありません。
高額査定されやすい作品の特徴とは?
松井康成の作品で特に高値がつきやすいのは、以下のような特徴を持ったものです。
-
模様が複雑で色数が多い作品
-
サイズが大きく、存在感のある作品
-
練上手の代表的な技法(破調練上、晴白練上など)を使っている
-
晩年期のもの、個展に出品された作品
-
共箱や鑑定書など、付属品が揃っているもの
逆に、付属品が欠けているものや傷・欠けがある作品、経年劣化が目立つものは、査定額が下がる可能性もあります。
もしご自宅に松井康成の作品があり、売却をお考えであれば、専門業者にしっかり査定を依頼するのが安心です。価値ある逸品を見逃さないためにも、信頼できる鑑定士のいる店舗を選ぶと良いでしょう。
技術は次世代へ ― 息子・松井康陽の継承
松井康成の没後、その技術を引き継いだのが長男・松井康陽(こうよう)氏です。彼もまた陶芸の道を歩み、練上手の世界をさらに発展させています。
父が多色使いを得意としたのに対し、康陽氏の作品はよりシンプルで力強い模様構成が特徴。特に直線や幾何学的な模様を活かした作品には、モダンで洗練された空気が漂います。
その個性と技術の高さから、康陽氏の作品も近年では高く評価されており、展覧会でもたびたび注目を集めています。
まとめ
松井康成は、単にひとつの技術を完成させた作家ではありません。練上手という古くからある技法に現代的な感性と革新性を吹き込み、芸術としての“深み”を与えました。
陶土の不確かさを味方にし、模様の偶然性を美に変えるその作風は、日本の陶芸史の中でも特異な存在です。そして、その世界観を支えていたのは、何十年にもわたる試行錯誤と、職人としての執念ともいえる技術探求でした。
現在、松井康成の作品は国内外の骨董市場で高く評価され続けており、とくに練上手の大作や晩年の作品は貴重な文化遺産としての価値も帯び始めています。
もし、ご自宅に松井康成の作品が眠っているのなら、それは単なる「器」ではなく、時代とともに磨かれた一つの芸術品。
その背景や価値を知ることで、きっとその魅力をもっと深く感じられるはずです。