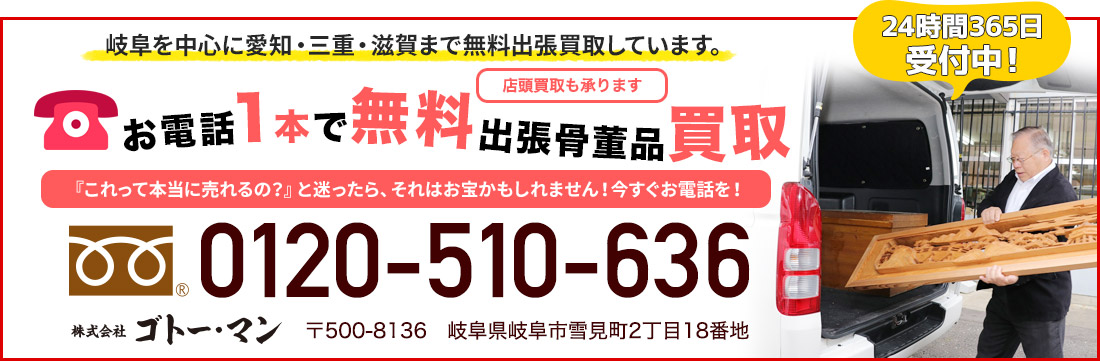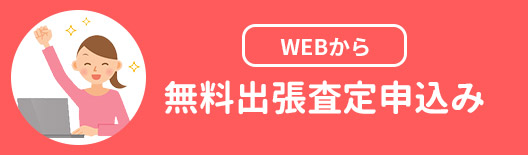骨董好き必見!古伊万里の魅力と価値を見極めるポイント
江戸時代に誕生した古伊万里の魅力や価値、見極め方と現在の買取相場をご紹介します。
骨董の世界に足を踏み入れると、必ずどこかで耳にする「古伊万里」という名前。
一見すると、単なる美しい焼き物に見えるかもしれませんが、そこに宿る歴史や技術、そして作り手たちの情熱は、現代の私たちの想像を遥かに超えるものです。
「これは本物なのか?」「どんなところに価値があるの?」
そう疑問に思った方のために、今回は古伊万里の魅力や歴史、見分け方や現在の買取相場について、できるだけわかりやすく、そして熱量を込めてお話ししていきます。
古伊万里とは?日本が誇る最初の磁器
古伊万里とは、江戸時代初期から中期にかけて、現在の佐賀県有田町を中心とした地域で焼かれ、伊万里港から出荷された磁器のうち、特に古いものを指す通称です。
日本で最初に作られた磁器として知られ、藍色一色の染付から、金彩をふんだんに使った色絵まで、時代とともにさまざまな様式が発展していきました。
特徴
古伊万里の最大の魅力は、その「文様の美しさと多様性」です。
-
藍色だけで描かれた染付(そめつけ)
-
色絵と金彩を用いた華やかな金襴手(きんらんで)
-
白磁に赤・緑・黄の配色が美しい柿右衛門様式
-
窓絵や草花、動物、幾何学模様などの大胆な構図
なかには、余白のないほどびっしりと文様が描き込まれた器もあり、時代の豊かさと職人の遊び心が感じられます。
古伊万里と伊万里の違い
ここでよくある疑問。「古伊万里と伊万里って、何が違うの?」
古伊万里は、17〜18世紀ごろの有田焼のうち、特に古い時代に作られたものを指します。一方、伊万里焼は時代を問わず、伊万里港から出荷された磁器全般を表す言葉。つまり、古伊万里は伊万里焼の一部であり、時代によって区別されているということですね。
古伊万里のほうが、骨董としての価値が高く評価されることが多く、買取価格にも反映されています。
古伊万里の歴史をひもとく
古伊万里のルーツは、17世紀初頭。朝鮮から渡来した陶工たちが、九州の地に磁器の技術を伝えたのが始まりです。
当初は藍一色の染付磁器が中心でしたが、やがて中国の技術や美意識が取り入れられ、色絵磁器が生まれます。このころに発展したのが、柿右衛門様式や金襴手様式です。
その後、ヨーロッパへの輸出も本格化。オランダ東インド会社を通じて世界中に輸出され、ヨーロッパの貴族たちを夢中にさせたといいます。
特に「赤絵」「金彩」が施された豪華な器は、今でも欧州の城館で見かけることがあります。
しかし、18世紀になると中国磁器の復活やヨーロッパの自国生産の発展により、輸出は次第に縮小。その後は国内需要を満たす方向へとシフトし、庶民の日常に寄り添う食器も多く作られるようになりました。
古伊万里の買取相場はどれくらい?
「家に代々伝わる器があるけど、これって値段つくのかな?」
気になるのが、古伊万里の買取相場ですよね。結論からいえば、その価格はピンからキリまで。数万円で取引されることもあれば、百万円を超える査定額がつくこともあります。
相場の目安
-
小皿や湯呑などの小品:1万円〜5万円前後
-
色絵の中型皿や壺:10万円〜30万円
-
初期伊万里、柿右衛門様式、大型壺など:30万円〜100万円以上
-
特別な作品(共箱・裏印・鑑定書付き):100万円以上
やはり高額査定が出やすいのは、歴史的に評価の高い様式や、保存状態が極めて良好なもの。そして、由緒ある箱や印、鑑定書などが揃っている作品です。
高く評価される古伊万里の種類と特徴
では、どんな古伊万里が高く評価されるのでしょうか?
初期伊万里
藍色一色の染付が特徴。17世紀初頭のもので、今では極めて希少です。焼成技術も未熟だった時代のため、形のゆがみや釉薬のムラも見どころのひとつ。
柿右衛門様式
白磁に赤・緑・黄などを配色し、動植物や風景を描いた華やかなスタイル。酒井田柿右衛門によって完成され、現代でもファンが多い作品群です。
金襴手様式
金彩を豪華に施した贅沢な器。海外輸出用にも多数作られ、現在ではその豪奢さから骨董ファンに根強い人気を誇ります。
裏印や付属品の有無
裏印(落款)や共箱・共布・鑑定書などの付属品があると、作品の真贋が明確になるため、買取額が大きく跳ね上がる傾向にあります。
偽物の古伊万里を見抜くポイント
市場で高値がつく古伊万里。だからこそ、偽物も数多く出回っています。
1. 表面の光沢
江戸時代の磁器は長年の経年変化により、表面の光沢が程よく落ち着いています。
不自然なツヤツヤ感がある場合は、近年のレプリカの可能性あり。
2. ゆがみの有無
手作業で焼かれた古伊万里は、器の口や底に微妙なゆがみがあります。完全な円形や対称性を持つものは、機械で作られた現代物かもしれません。
3. 小さなキズ
200年以上もの時を経ている焼き物には、細かなキズや釉薬の剥がれなどが見られます。これが全くない場合、不自然に感じられることもあります。
※ただし、あくまで目安です。近年の贋作は非常に精巧なため、最終的な判断は専門家に任せるのが賢明です。
古伊万里を売るときに気をつけたいこと
せっかく価値ある古伊万里を売るなら、適切な方法で査定してもらいたいですよね。
-
査定時は共箱や鑑定書も一緒に提出
-
状態を無理に磨いたりせず、現状のままで
-
専門の骨董商や信頼できる鑑定士に依頼する
-
相見積もりを取る(複数の業者で比較)
こうした基本的なポイントを押さえるだけでも、査定結果は大きく変わります。できれば古伊万里に詳しい店舗にお願いしたいところです。
まとめ
古伊万里は、単なる“器”ではありません。
そこには職人の技術、時代背景、そして美の哲学が詰まっています。
たとえば、形のゆがみひとつにしても、江戸時代の釜の温度管理の難しさが垣間見える。色彩の鮮やかさには、海を越えて憧れたヨーロッパ貴族のまなざしが宿っている。
そう考えると、古伊万里の器は“歴史を使う”という行為そのものだとすら思えてきます。
これから古伊万里に触れる方は、まずは一客を手に取ってみてください。
そして、その“重み”に耳を澄ませてみてください。
きっと、数百年の時を超えて語りかけてくるものがあるはずです。
美しいものを“知る”喜びが、ここにあります。