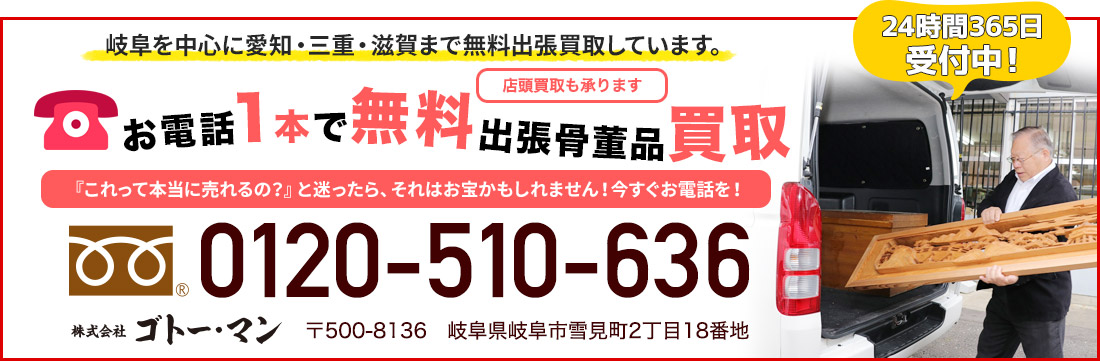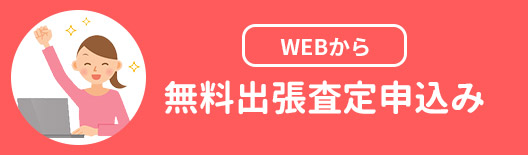有田焼と伊万里焼の違いは?産地・歴史についてわかりやすく解説
有田焼と伊万里焼についてご紹介します。
日本の伝統の焼き物の1つである有田焼と伊万里焼(いまりやき)。どちらも佐賀県生まれの焼き物ですが、名前だけ聞くと別の焼き物だと思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし実は、有田焼と伊万里焼は同じもので、それぞれ呼び方が違うというだけなのです。
同じ焼き物なのに2つの呼び名がある理由は、その由来にあります。
有田焼と伊万里焼の違いは「呼び名」
有田焼の名前の由来
有田焼という名は、磁器が初めて焼かれた土地「有田」にちなんで名付けられました。
ここで生まれた磁器が日本中に広まり、やがてヨーロッパへも輸出されるほど広く知られるようになりました。
伊万里焼の名前の由来
一方、伊万里焼(いまりやき)という呼び名が生まれたのは、焼き物の輸出港が「伊万里港」だったことが理由です。有田で作られた磁器は、近隣の伊万里港から全国・海外へと出荷されていたのです。
この出荷地の名前が焼き物の名称として広まり、とくにヨーロッパでは「伊万里焼(Imari)」の名前で知られるようになりました。
つまり、「有田で作られ、伊万里から出荷された磁器」だったため、作られた場所の名前である”有田焼”と、出荷された港の名前にちなんだ”伊万里焼”という、2つの呼び名が使われるようになったのです。
歴史的な背景
有田焼の歴史は、戦国末期にさかのぼります。
16世紀末、豊臣秀吉は朝鮮出兵の際に、当時の日本では難しいとされていた硬くて薄い焼き物を作るため、朝鮮の陶工達を連れて帰りました。
佐賀の藩祖であった鍋島直茂も同じ理由で朝鮮の陶工達をつれて帰り、そのまま有田に住み続けることとなった彼らが有田の土でつくった陶器が有田焼です。
さらにその陶器の技術に磨きをかけていくにつれ、貿易をおこなっていた東インド会社からも注目されるような素晴らしい焼物へと成長していき、「伊万里焼」の名で世界に知られるようになりました。
現在の有田焼と伊万里焼
これまでご紹介したように、かつては同じものとされていた有田焼と伊万里焼ですが、現在ではそれぞれの製造地に基づいて呼び分けられています。
有田町で作られたものは「有田焼」、伊万里市で作られたものは「伊万里焼」と呼ばれ、それぞれが独自の技術やデザインを進化させながら現代に受け継がれています。
有田焼・伊万里焼の伝統的な特徴
原材料
焼き物はその使用する材料の土によって種類が異なり、陶土からつくられたものは陶器、陶石からつくられたものは磁器となります。
有田焼・伊万里焼の場合は陶石からつくられているので、磁器にあたります。
この磁器の原料となっている有田産の泉山陶石や天草陶石は他の土を混ぜる必要がなく、1種類の陶石単体でつくれる石は他にないとされており、これが有田焼の品質を急成長させた理由です。
耐久性
有田焼・伊万里焼は、陶石の性質から耐久性がとても高いです。他の陶磁器よりも軽いのに丈夫でさらに薄いと、食器として非常に素晴らしい焼き物とされています。
肌触り
有田の陶石は白磁という名前の通り材料の陶石も白く美しい種類のものです。そのため焼き上がりも肌触りもツルツルとして心地よく、その表面はまるでガラスのよう。
丈夫というだけでなく質感でも芸術的な面があり、当時では大名や将軍にも愛され、献上品や贈答品として珍重されていました。
まとめ
有田の素晴らしい土でつくられ、焼き物として非常に上質なものへと発展し伊万里の港から輸出されるまでとなった有田焼、伊万里焼。
今でも皇室献上品として選ばれることもあり、伝統を守りながらも日本を代表する焼き物として現代でも進化しているのです。